
市場の名はどこから?古代から中世の記憶
現在の鶴見市場周辺、特に市場大和町や市場下町といった地名の「市場」は、その名の通り、かつて賑わいを見せた**市(いち)**の存在に由来します。
この市が開かれた歴史は非常に古く、古代にまで遡ります。平安時代中期に編纂された『和名抄(わみょうしょう)』には、この一帯が「武蔵国橘樹郡(たちばなぐん)楊野郷(やぎのごう)」に属していたことが記されています。この「楊野郷」の時代から、近隣の集落との間で、生活物資の交換が行われる場所、すなわち「市」が自然発生的に形成されていたと考えられています。
特に中世に入ると、この地は**「川崎宿」と「神奈川宿」という二つの重要な宿場町の中間に位置し、海路・陸路の要衝として栄えました。現在の鶴見川の河口近く、現在の市場下町や市場富士見町**のあたりは、水運の便も良く、地域の特産品や海産物などが集まる商業の中心地として、その役割をさらに強めていきました。この活発な経済活動が、この地域に「市場」という名を定着させたのです。

江戸時代:東海道と宿場間の賑わい
江戸時代に入ると、五街道の一つである東海道が整備され、この地域の重要性が一層高まります。東海道は、現在の市場上町や市場西中町付近を通り、人や物資の往来が激しくなりました。
しかし、鶴見市場自体は宿場町には指定されませんでした。そのため、川崎宿と神奈川宿の間に位置する**間の宿(あいのしゅく)**のような形で、旅人や商人たちを相手にした茶屋や商店が立ち並び、独特の賑わいを見せていました。
また、内陸部の農村地帯と、鶴見川を利用した水運の結節点でもあったため、物資の集散地としての機能は維持され、江戸時代の物流を支える隠れた要衝でもあったのです。
近代の変遷:工業化と住宅地の形成
明治時代に入り、日本が近代化の波に乗り出すと、鶴見市場エリアも大きな変貌を遂げます。
まず、1905年(明治38年)に京浜電気鉄道(現在の京急線)の駅として鶴見市場駅が開業しました。これにより、横浜や東京へのアクセスが飛躍的に向上し、人々の生活スタイルが大きく変化します。
さらに、大正時代から昭和初期にかけては、京浜工業地帯の一部として、周辺の平安町や菅沢町などの臨海部で大規模な埋め立てが進み、重工業の工場が数多く進出しました。これらの工場で働く人々が増加したことで、鶴見市場エリアは、単なる商業地から、急速に工業と住宅が混在する地域へと姿を変えていきました。
特に、市場大和町や市場西中町といった内陸部では、工場労働者向けの住宅や商店が増加し、地域の人口も大きく増加しました。かつての「市」の面影は薄れつつも、人々が集まり生活を営む活気は途絶えることがありませんでした。
現代の鶴見市場:歴史を受け継ぐ街並み
戦後の復興と高度経済成長を経て、鶴見市場エリアは現在に至ります。
現代の市場上町、市場下町、市場西中町、そして市場富士見町などの「市場」を冠する町名は、古来からの商業的な活気の記憶を今に伝えています。また、平安町や菅沢町の工業地帯は、日本の経済を支え続けています。
鶴見市場は、古代からの「市」の機能、東海道という大動脈のそばでの発展、そして近代の工業化という、日本の歴史における重要な転換期の全てを経験してきた地域です。
街を歩くと、京急線の高架下にある昔ながらの商店街の活気や、静かな住宅街のたたずまいの中に、時代ごとの記憶の断片を見つけることができます。
鶴見市場は、過去の歴史を大切にしながら、これからも発展し続ける魅力的な街です。次回この地を訪れる際は、ぜひ「市場」という地名の重みに思いを馳せてみてください。







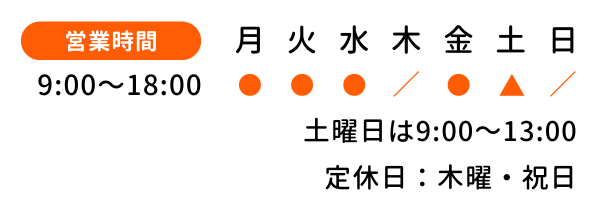
この記事へのコメントはありません。